土地や遺産の「所有権」を巡るトラブルとは?具体例と回避する方法
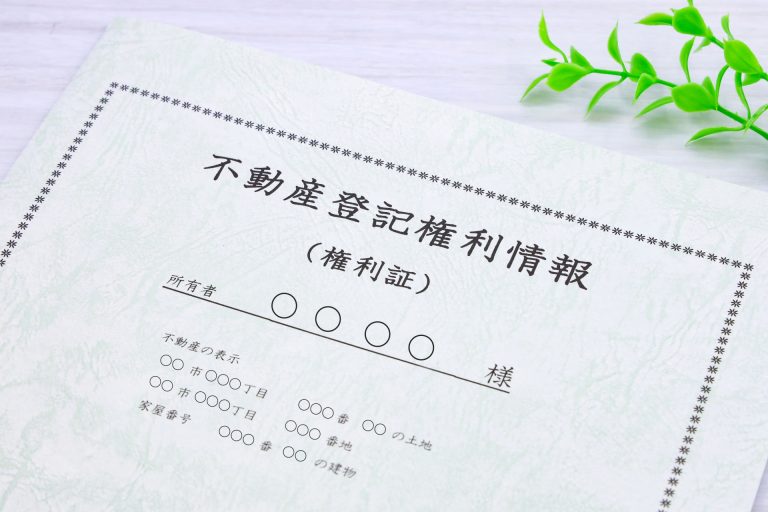
目次
遺産の所有権問題は、相続や購入時に発生しやすく、多くの人が遭遇する可能性があります。
特に土地のような不動産は物理的に分割することが難しいため、余計にトラブルに発展しやすいと言われています。
本記事では、所有権に関するトラブルの例と、具体的な回避方法を紹介します。
【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
そもそも所有権とは?
所有権は、対象物を自由に使用し、収益を得て処分できる権利のことです。
不動産の所有者には所有権が与えられており、所有権は法令上の制限の範囲内で、公共の福祉に反しなければ自由に行使できます。
ただし、所有権を有する地主は土地に他人の権利(抵当権※1・借地権※2など)が付着している場合、その行使に関していくつかの制限を受けます。
一方、借地人は土地の上に建っている建物の増改築が自由にできないなどの制約があります。
※1 抵当権とは、住宅ローンなどを借りる借主に対して、購入する土地や建物を担保とする権利のことです。何らかの理由でローンの返済ができなくなった際は金融機関が土地と建物を差し押えて強制競売にかけられます。
※2 借地権とは、建物の所有を目的に土地を借りる権利のことです。借地権が設定されている場合、土地と建物の所有者が別になります。
不動産の所有権にまつわる代表的なトラブル
不動産の所有権を巡ってトラブルが生じることも少なくありません。
こうしたトラブルは、不動産の所有者に多大なストレスをもたらすほか、経済的損失を被る可能性もあります。
不動産の所有権にまつわる代表的なトラブルは、以下の通りです。
- 所有権移転登記
- 土地の契約不適合(瑕疵)
- 境界紛争
トラブル①:所有権移転登記
土地を購入して所有権移転登記をする際にトラブルが起きるケースがあります。
具体的には、売主が同じ不動産を複数の人に二重に契約して譲渡してしまったときです。
こうしたトラブルは二重売買(二重譲渡)と呼ばれています。
民法の原則では、土地の所有権を第三者に対抗できるのは、先に所有権移転登記を具備した人です(民法第177条)。
そのため、登記をしていなかった(あるいは登記が遅れた)買主は「代金は支払ったのに土地の所有権が得られない」という状況に陥ります。
このような場合、所有権を得られなかった買主は、売主に対して支払った代金の返還や損害賠償を請求することが考えられます。
ただし、これにより購入しようとした土地の所有権が得られるわけではなく、金銭的な解決が図られることが一般的です。
トラブル②:土地の契約不適合(瑕疵)
土地の瑕疵トラブルとは、購入前に知らされていなかった土地の欠陥や法的な制約事項が後から発見されることで発生するトラブルです。
これは、土地の売買契約を締結する過程で、売主が土地の隠れた欠陥や重要な制約事項を買主に伝えていなかったために発生します。
例えば、地中に予期せぬ廃棄物が埋もれていたり、土壌が有害物質に汚染されていたり、あるいは法律による建築制限があるにもかかわらず、それを伝えなかったケースなどです。
このような契約内容に適合しない事実(契約不適合)が明らかになった場合、買主は売主に対して追完請求(修補など)、代金減額請求、損害賠償請求、そして場合によっては契約の解除を求める権利があります。
この際、売主は契約不適合責任を負うことになります。
トラブル③:境界紛争
境界トラブルは、特に相続の時に顕在化しやすい問題ですが、土地の売買時や日常生活においても発生する可能性があります。
これは、隣接する土地同士の境界が曖昧になっていることが主な原因です。
特に、樹木や塀などが境界線を越えて相手の土地にはみ出してしまっている場合、隣人との揉め事に発展しやすく、このようなトラブルは「境界紛争」とも呼ばれます。
かつては、境界を越えている樹木や構造物を勝手に撤去したり処分したりすることは認められていませんでしたが、令和5年4月1日から施行された改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)により、状況が変わりました。
この改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に越境した枝の切除を求めても応じない場合や、竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合、あるいは急迫の事情がある場合など、一定の条件下では自らその枝を切り取ることが可能になりました。
なお、根については従来から一定の条件下で自ら切り取ることが認められていましたが、枝に関する要件はこの改正で緩和された形となります。
境界紛争が発生する具体的な原因としては、主に隣接する土地の境界(筆界)が不明確であることや、境界を客観的に示す資料(例えば、境界標や地積測量図など)が不足していること、または当事者間での境界に対する認識が異なっていることなどが挙げられます。
つまり、どこまでが自分の土地で、どこからが隣人の土地なのかがはっきりしない状態が、問題を引き起こしているのです。
このような境界に関するトラブルを未然に防ぐためには、土地の境界を明確にしておくことが不可欠です。
そのための具体的な方法としては、土地家屋調査士に依頼して正確な測量を行い、その上で隣接する土地の所有者と共に境界の立会いを行い、境界について合意することが重要です。
そして、隣地所有者の立会いのもとで確定した境界については、その結果を境界確認書といった書面で残しておくことが望ましいでしょう。
【4万件超の実績とノウハウ】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫
不動産の所有権にまつわるトラブルを回避するためのポイント
土地などの不動産の所有権に関するトラブルの多くは、事前に適切な対応をすることで未然に防げるものも少なくありません。
不動産の所有権にまつわるトラブルを回避するためのポイントは、以下の通りです。
- 決済手続きは慎重に行う
- 購入する土地や物件に関する疑問点を解消しておく
- 解決が難しい際は専門家の力を借りる
ポイント①:決済手続きは慎重に行う
土地を売買する際は、自分が不利にならないように決済手続きを慎重に行うようにしましょう。
例えば、売買契約書の内容に不利な条項が含まれていたり、書面に不明瞭な表現があったりした場合は要注意です。
一度サインしてしまうと原則として契約内容を認めたことになるからです。
したがって、契約を締結する前に、契約書の条項、特に特約事項に著しく自分に不利な内容がないことを確認し、疑問点があれば専門家にも相談するなどして自分の不利益を避けるよう努めましょう。
また、所有権移転登記手続きと売買代金の決済は同時に行うこと(いわゆる「同時決済」)を強くおすすめします。
同時に行うと取引(同時履行)の透明性と安全性を確保でき、トラブルを防げるからです。
ポイント②:購入する土地や物件に関する疑問点を解消しておく
土地や物件の購入の際は、すべての疑問点を解消するようにしましょう
購入後に発生するトラブルを未然に防ぐためには、事前の確認が不可欠だからです。
特に売主の契約不適合責任に関する条項は重要な確認ポイントです。
売主が責任を負う期間に制限を設けている場合、それが買主にとって不利に働く可能性があります。
事前にしっかりと内容を理解し、納得できるまでチェックしておきましょう。
また、購入する土地や建物に関して不明点がある場合は、必ず売主に尋ねるようにしましょう。
例えば、土地の境界線に関する疑問や建物の構造に関する質問など、不安を感じた点は何でも質問するべきです。
必要に応じて、自身で役所調査を行ったり、専門家(建築士など)による建物状況調査(インスペクション)を依頼したりすることも検討しましょう。
ポイント③:解決が難しい際は専門家の力を借りる
トラブルの内容によってはお互いが権利を主張して議論が進展しないことも考えられます。
お互いが感情的になりそうな事案や、問題が複雑に絡んでいる事案は、早めに専門家に相談し、サポートを求めるのが有効な手段です。
専門家は、法律に基づいた客観的な見解から、問題解決に向けた具体的なアドバイスや、必要に応じて交渉や法的手続きの代理を行ってくれます。
弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
なお、当社センチュリー21中央プロパティーには、借地権を専門とする社内弁護士が常駐しており、いつでも法的な観点からのアドバイスが可能です。
また、司法書士や税理士、不動産調査士といった各種士業との連携により、借地権トラブル・借地権売却を確実にサポートいたします。
相談から売却まで料金は一切いただいておりませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
センチュリー21中央プロパティーに所属する借地権の専門家はこちら ≫
所有権を侵害された場合の対処法は?行使できる3つの権利
もし所有権を侵害された場合は、法的な救済を求める権利があります。
所有権侵害に対して行使が認められているのは、以下の権利です。
- 物権的請求権
- 損害賠償請求権
- 不当利得返還請求権
所有権の侵害に対して行使できる権利①:物権的請求権
物権的請求権は、所有権が侵害された際に行使できる法的権利です。
物権的請求権には、以下の3つの権利が含まれます。
- 返還請求権
- 妨害排除請求権
- 妨害予防請求権
物権的請求権の内容(1):返還請求権
自分の所有物が権原なく他人に占有されている場合、所有物の返還を請求することができます。
これは、所有者がその物の占有を失っている場合に認められる権利です。
例えば、自分の土地が他人に無断で占拠されている場合や、動産が盗まれた場合などに行使されます。
返還請求によって、所有物を正当な所有者の手に戻すことが可能となります。
返還請求を受けた者は、その物の占有を止め、所有者に引き渡さなければなりません。
物権的請求権の内容(2):妨害排除請求権
所有物の占有以外の方法で所有権の円満な行使が妨げられている場合、その妨害を排除するよう請求することができます。
この請求は、所有権の行使を妨害されているときに認められる権利です。
例えば、所有する土地に隣人がゴミを不法に投棄しているのが発覚した際には、妨害排除請求を行使してゴミの除去を求めることができます。
妨害排除請求を受けた者は、所有権を妨害している状態を解消しなければなりません。
物権的請求権の内容(3):妨害予防請求権
妨害予防請求とは、自分の所有権が将来的に侵害されるおそれがある場合に、その予防措置を求めることができる権利です。
この請求は、所有権が実際に侵害される前の段階で行使できる点が特徴です。
具体例を挙げると、隣地の所有者が危険な工事を行っており、その結果、自宅が損傷するおそれがある場合などに、安全措置を講じるよう妨害予防請求ができます。
所有権の侵害に対して行使できる権利②:損害賠償請求権
所有権侵害により損害を被った場合、侵害者に対して損害賠償請求が認められます。
これには、侵害者による故意または過失が必要です(不法行為責任)。
例えば、所有する土地に他人が無断で建設機械を持ち込み、その結果として土地が損傷したとします。
このような場合、土地の原状回復費用や、土地が使用できなかった期間の逸失利益などを損害賠償請求によって補償してもらうことができます。
借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫
所有権の侵害に対して行使できる権利③:不当利得返還請求権
不当利得返還請求とは、他人が法律上の原因なく不当に得た利益を返還するよう請求できる権利のことを指します。
不当利得とは、法律上で認められた権利がないにもかかわらず、他人に損失を被らせて得た利益のことです。
例えば、隣人があなたの土地を無断で駐車場として第三者に貸し出し、その結果収益を上げた場合、それは不当利得とみなされます。
このようなケースでは、不当利得返還請求を行うことで、隣人が得た収益の返還を請求できます。
【無料相談】地主から建て替え・増改築の承諾が得られずお困りの方はこちら ≫
所有権トラブルを回避するために疑問点は必ず解決しよう
本記事では、所有権を巡る様々なトラブル事例と、それらを未然に防ぐための具体的な対策を解説しました。
ご紹介したように、所有権に関する問題の多くは、初期の小さな疑問やちょっとした違和感に早めに気づき、対処することで回避できる可能性があります。
「おかしいな?」と感じたら決して放置せず、納得できるまで確認する姿勢が大切です。
しかし、所有権の問題は複雑で、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいケースも少なくありません。
そのような場合は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることをためらわないでください。
特に、遺産相続や不動産の購入といった重要な場面では、まず専門家に相談し、潜んでいるリスクを正確に把握することが、将来の安心につながります。
当社センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。
これまでに携わった借地権トラブル・売却相談の総数は4万件を超え、借地権関連のノウハウは他社の追随を許しません。
社内弁護士や司法書士など、各種士業とのスムーズかつ強固な連携により、権利関係が複雑と言われることも多い借地権のトラブル解決・好条件での売却をしっかりとサポートさせていただきます。
相談から売却まで、一切料金を頂戴しない独自のシステムをとっておりますので、借地権に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【ご相談~売却まで完全無料!】借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!「借地権のトラブル解決マニュアル」では、トラブルの対処法や当社のサポート内容を紹介しています。ぜひご覧ください。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。





