借地権の建替承諾料の相場はいくら?承諾料が不要なケースとは
借地権の建替承諾料の相場はいくら?承諾料が不要なケースとは

目次
建替承諾料(増改築承諾料)とは、借地人が借地上の建物を建て替えたり大規模な増改築を行ったりする際に、地主に支払うお金のことです。
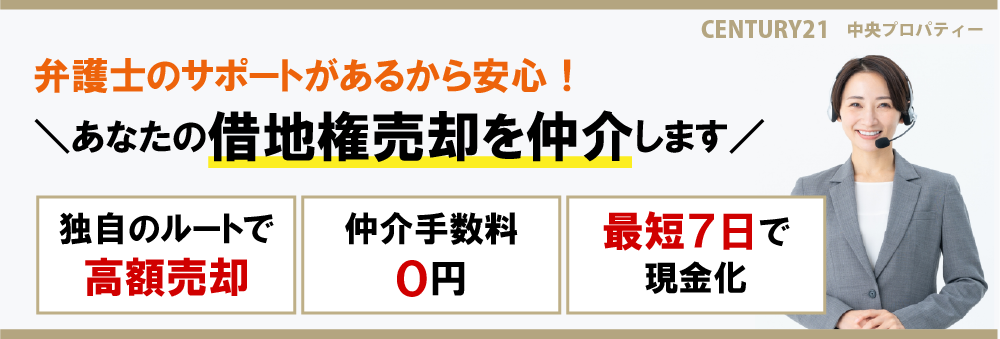
借りている土地の上にある建物を建て替える際、地主の承諾は必要なのでしょうか。
この記事では、借地権の建て替え承諾の必要性や承諾料の目安、建て替え時の注意点についてわかりやすく解説します。
借地権付き建物の建て替えに地主の承諾は必要?

借地権付き建物の建て替えには、原則として地主の許可が必要です。
しかし、例外的に許可が不要なケースもあります。
地主の許可が必要なケース
借地上の建物の建て替えについて、地主の許可が必要なケースは以下の3つです。
- 借地条件の変更を伴う建て替えの場合
- 増改築禁止の特約がある場合
- 更新後の場合
無断で建て替えを行った場合、借地契約の解除、さらには建物収去土地明渡請求をされる可能性があります。
そうなると、借地権を失うだけではなく、建物の解体工事費も負担しなければならない可能性があるため注意しましょう。
借地条件の変更を伴う建て替えの場合
借地条件の変更とは、「非堅固建物(木造等)から堅固建物(鉄骨造等)への建て替え」など、契約書に定められた条件変更を指します。
居住用から事業用へと建物の用途を変更する場合も条件の変更と見なされます。
借地条件の変更は、「建物の耐用年数(存続期間)に大きな変化をもたらす」「用途の変更によって地主に不都合が生じる」などの可能性があるため、地主の承諾が必要です。
増改築禁止の特約がある場合
借地に関する法律(借地借家法)においては、建て替えに地主の承諾が必要であるという直接的な文言はありませんが、増改築に関する制限は、契約の特約として規定されることが一般的です。
通常、借地契約では「増改築禁止の特約」が定められており、建て替えや増改築には、事前に地主の承諾が必要です。
経年劣化などによる単なる修繕であれば、地主の許可は不要です。
しかし、修繕の規模によっては「改築」と見なされる場合もあるため注意しましょう。
更新後の場合
契約書で「増改築禁止の特約」が規定されておらず、地主の許可なく建て替えできる契約だったとしても、契約更新後の増改築には、原則として地主の承諾が必要です。
つまり、特約がない場合でも、地主の許可なく建て替えができるのは最初の契約期間(借地借家法上の当初の存続期間)のみで、契約更新後は、地主の承諾なく建て替えを行うことはできません。
承諾のもらい方としては、地主に対し「借地上の建物を建て替えたい」旨を通知します。
その後、2か月以内に地主から異議申し立てがなければ、「地主は建て替えを承諾した」とみなされます。(借地借家法第7条2項)
地主の許可が不要なケース
借地上の建物の再築に、地主の許可が不要なケースは以下の通りです。
- 契約に特約がない場合
- 更新前の借地の場合
契約に特約がない場合
非常に稀なケースではありますが、借地契約書に「増改築禁止特約」が記載されていない場合、原則として地主の許可なく建て替えを行うことが可能です。
しかし、建て替えによって建物の耐用年数が契約期間を越えて著しく延びるなど、地主の利益を大きく害する可能性がある場合には、地主が異議申し立てを行う可能性もあります。
このような場合、最終的には裁判所の判断(主に借地非訟)になることもありますが、事前にトラブルを避けるためにも、地主とよく話し合い、合意を得ておくことが望ましいです。
更新前の借地の場合
借地権の更新前、つまり契約における最初の存続期間中は、増改築禁止の特約がなければ地主の許可なく建て替えをすることが可能です。
ここで注意したいのが、借地契約の残存期間と建て替える建物の耐用年数の関係です。
例えば、契約残存期間が20年の借地に30年住むつもりの家(耐用年数30年の建物)を建てた場合、
- 地主の許可を得ている場合:借地期間が延長される、または建物買取請求権を行使できる可能性があります。
- 地主の許可を得ていない場合:契約が更新されない、または不利な条件での更新になる可能性があります。
1992年7月31日以前の旧法が適用される契約では増改築禁止の特約を定めていない契約も多くありますが、許可なく建て替えできると安易に判断しないよう気をつけましょう。
借地権の建替承諾料(増改築承諾料)とは
建替承諾料(増改築承諾料)とは、借地上の建物を建て替えたり大規模な増改築を行ったりする際に、地主に支払うお金のことです。
新しい建物が建築または増築されることで、借地権の評価や土地の利用状況に影響を与える場合があり、地主がそれに対する対価として、建替承諾料を請求することがあります。
建替承諾料の支払いが必要なケース
建替承諾料が求められることがある主なケースは、以下の通りです。
| 借地契約で「建て替えには地主の承諾が必要」と定められている場合・・・ このような契約の場合、借地人が建て替えを行う際に、地主から承諾料の支払いを求められることが一般的です。 |
| 建物の構造や規模を大幅に変更する場合・・・ 例えば、木造の2階建てから鉄筋コンクリート造の4階建てに変更するような場合、土地の利用状況や借地権の価値が大きく変わることから、地主の承諾が必要となり、承諾料の支払いが必要となる場合があります。 |
承諾料の支払いについて、法律上の明確な規定はありませんが、過去の判例や実務上の慣習として、地主が請求することが一般的とされています。
ただし、承諾料の金額や支払いの要否については、借地人と地主の合意によって決まるため、交渉の余地がないわけではありません。
建替承諾料の支払いが不要なケース
一方で建替承諾料が不要と考えられるケースも存在します。
| 小規模な修繕や軽微な改築の場合・・・ 壁のひび割れ修理や窓枠の交換など、建物の主要構造部分に影響しないような修繕は増改築に該当しません。 したがって、建替承諾料の支払いは不要となるのが一般的です。 |
| 地主との間で承諾料が不要であると合意を取っている場合・・ 先述した通り、承諾料の金額や支払いの要否は借地人と地主の合意によって決まります。 そのため、極めて稀なケースではあるものの、契約書に建替承諾料の支払いを要しない旨が明記されている場合は支払い不要です※。 例えば、地主と借地人が親族の関係にあるときに、承諾料を請求しない旨の合意が交わされることがあります。 ※ただし注意点として、たとえ事前に当事者間で承諾料を不要とする合意があったとしても、実際に地主の承諾が得られず裁判所に許可を求める手続き(借地非訟)になった場合、裁判所は許可の条件として相当額の承諾料(財産上の給付)の支払いを命じることが一般的です。 この点を踏まえると、承諾料は実質的には支払いが必要なもの、という側面が強いと言えるでしょう。 |
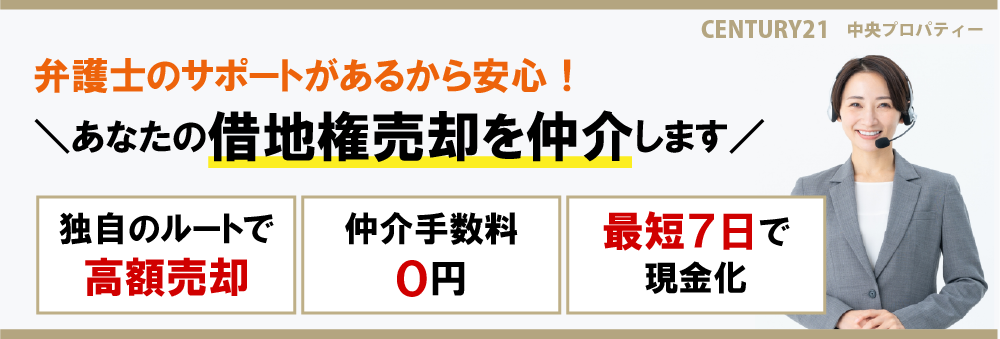
建替承諾料の相場はいくら?
建替承諾料の相場は、一般的に更地価格の3~5%程度とされています。
ちなみに更地価格とは、借地上の建物がない状態の土地の価格(=底地価格+借地権価格)のことです。
例えば、更地価格が1億円の土地の場合、建替承諾料は500万円~1200万円程度になると考えられます。
ただし、この相場はあくまで目安です。
最終的な金額は借地人と地主との交渉によって決定します。
また、建替承諾料の目安は、建物の構造(RC造、木造、鉄骨造など)によっても変わります。
加えて、個別の契約条件や地域の慣行も承諾料の金額に影響します。
一般的に、都市部では土地の価値が高いため、承諾料が高くなる傾向です。
そして、承諾料の交渉は、借地人と地主の立場や、これまでの関係性によっても左右されます。
長年良好な関係を築いてきた場合は、承諾料が低く抑えられるケースもあります。
反対に、過去にトラブルがあった場合は、交渉が難航することも考えられます。
借地権付き建物を建て替える際の注意点
借地権付き建物を建て替える際の注意点は、以下の通りです。
- そもそも建て替えができないケースがある
- 希望通りの建て替えが叶わないケースがある
- 建て替え時に借入れが困難
- 地代を増額される可能性がある
そもそも建て替えができないケースがある
建築基準法では、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接する必要があります(接道義務)。
この義務を満たさない土地は「再建築不可」となり、原則として建物の建て替えができません。
例えば、道路に接する通路部分の幅が2m未満の旗竿地などが該当します。
現在建物が建っていても、この義務を満たさない借地では建て替え自体が不可能となるため、計画前に必ず確認が必要です。
希望通りの建て替えが叶わないケースがある
建築時は適法でも、法改正等で現行の建築基準法に適合しなくなった建物を「既存不適格建築物」といいます。
容積率や建ぺい率、高さ制限が現行基準を超えている場合などです。
そのまま住むのは問題ありませんが、建て替えの際は現行法規に適合させる必要があります。
そのため、元の建物と同じ広さや高さで建てられず、規模を縮小しなければならないなど、希望通りの建て替えが叶わない可能性があります。
建て替え時に借入れが困難
借地権付きの建物を建て替える際、住宅ローンを検討する方も多いでしょう。
しかし、借地権であるがゆえに、融資を受けるのが非常に難しいという問題があります。
金融機関は、住宅ローンを貸す際に、地主に「融資承諾」を求めるのが一般的です。
融資承諾には、借地人が地代を滞納した場合、契約解除の前に金融機関に連絡を入れること、連絡がない場合は損害賠償を請求する、など地主にとってリスクとなる内容が含まれます。
そのため、融資承諾をしてくれない地主も半数ほど存在すると覚えておきましょう。
また、建て替えの承諾料を地主に支払ったにもかかわらず、融資に必要な地主の同意が得られず、結果的に建て替え費用を捻出できなくなるケースも存在します。
この場合、すでに支払った承諾料の返還を求めることは難しいため、注意が必要です。
地代を増額される可能性がある
建て替えの際に、非堅固建物から堅固建物に変更した場合、地代増額の可能性があります。
まず、契約内容は原則、当事者が自由に決めることができます(契約自由の原則)。
地主・借地人両者で従前の地代で同意ができれば、建物を建て替えても、地代への影響はありません。
地代については、法律の関するところではないため、当事者間での合意がそのまま反映されることになります。
ただし、地主の立場からすると、堅固な建物への建て替えにはリスクがあります。
例えば、非堅固建物である木造アパートから堅固建物である鉄筋コンクリートのビルに建て替える場合、丈夫な建物になるため、建物の寿命は大幅に伸び、土地が返ってくる可能性が低くなります。
また、建物買取請求権を行使された場合には、建物を買い取る金額も高騰することが考えられます。
そうなると、地主としては「地代を上げてもらわなければ納得がいかない!」という気持ちになることに不思議はありません。
建替承諾料(増改築承諾料)についてのよくあるご質問
Q.建替承諾料(増改築承諾料)の支払いは義務ですか?
A.借地上の建物の建て替えの際に、地主の承諾を得なければならない旨を定めた法律上の規定はありません。
しかしほとんどの借地契約書には、「建物の増改築を行う際には地主の承諾を要する」旨の特約が記載されており、契約に基づく義務として、地主の承諾が必要であり、地主の承諾なしに建て替えを行うことで契約解除となるリスクがあります。
Q.借地上の建物の増改築を地主に拒否されたらどうすべきですか?
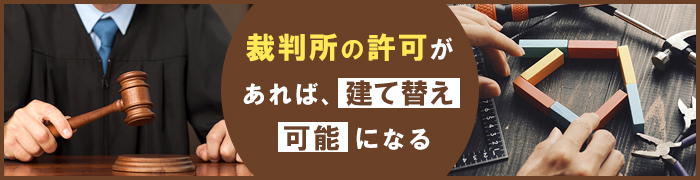
A.借地上の建物の増改築を地主に拒否された場合、借地人は裁判所で借地非訟(しゃくちひしょう)の手続きを申し立てることができます(借地借家法第17条、第18条)。
借地非訟とは、借地借家法に基づき、地主の承諾に代わる裁判所の許可を求めるための手続きです。
借地人は、裁判所に増改築の許可を求める申立てを行います。
申し立てが認められた場合、裁判所の許可に基づき、地主の承諾を得ることなく増改築が可能となります。
裁判所は、増改築の必要性や土地の利用状況への影響、借地権者と地主の利益のバランスなどを総合的に考慮して判断を下します。
例えば、建物の老朽化による安全性の問題や、借地人の生活環境の改善が必要な場合などは、増改築が認められやすい傾向にあります。
ただし、裁判所から申し立てが認められた場合でも、借地人から地主へ承諾料を支払うのが一般的である点には注意が必要です。
借地非訟は申し立てをするにも法律に関係する専門知識が必要とされるため、まずは弁護士や借地権を専門に扱う業者へ相談することをおすすめします。
建替承諾料を巡ってトラブルになった際は、借地権の専門家に相談しよう
借地権付きの建物の建て替えと、建替承諾料について解説しました。
借地権付きの建物を建て替えることは可能ですが、地主の承諾が必須です。
借地条件に変更がある、契約に特約がある、契約更新後に建て替えを行うといった場合は、必ず地主の承諾を得ましょう。
それ以外の場合であっても、トラブルを避けるため、地主に報告してから建て替えを行うのが無難です。
借地権に関するトラブルの解決には、法的な知識や交渉力が必要となるため、 専門家(弁護士、不動産鑑定士、借地権に詳しい不動産業者など)への相談が不可欠です。
借地権についてお悩みの方は、ぜひ一度センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。
借地や底地の売却だけでなく、建て替えに関するご相談、トラブル解決のサポートなど、借地権に関する様々なお悩みに、経験豊富な専門家がご対応いたします。
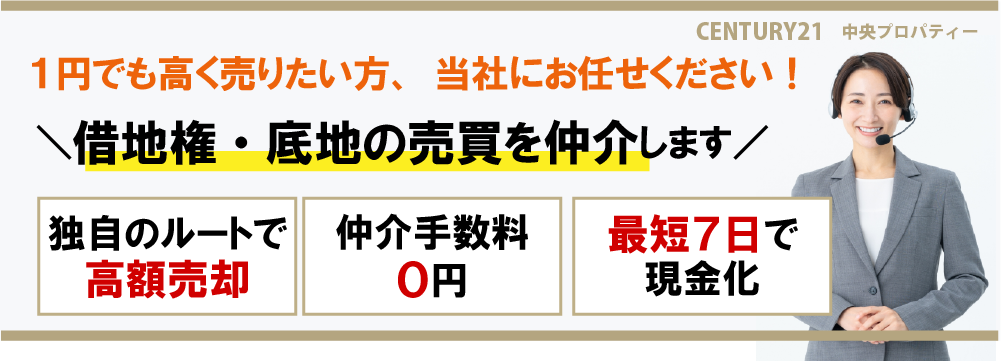
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。





