賃借権は相続できる?相続後の対応や起こりえるトラブルを解説
賃借権は相続できる?相続後の対応や起こりえるトラブルを解説

目次
土地や建物を貸し借りした際に発生する「賃借権」は、相続する財産にも含まれます。実際借地や貸し借りしている建物が相続されることになったとき、家賃や賃借権はどのように扱えばいいのでしょうか。
当記事では、賃借権を相続した際の対処方法と、賃借権の相続にまつわるトラブルについて解説します。特に借地を相続した際は、手続きが煩雑になったり地主とのトラブルが起きたりしやすい傾向にあります。相続について悩んだときは、専門家へ相談するようにしましょう。
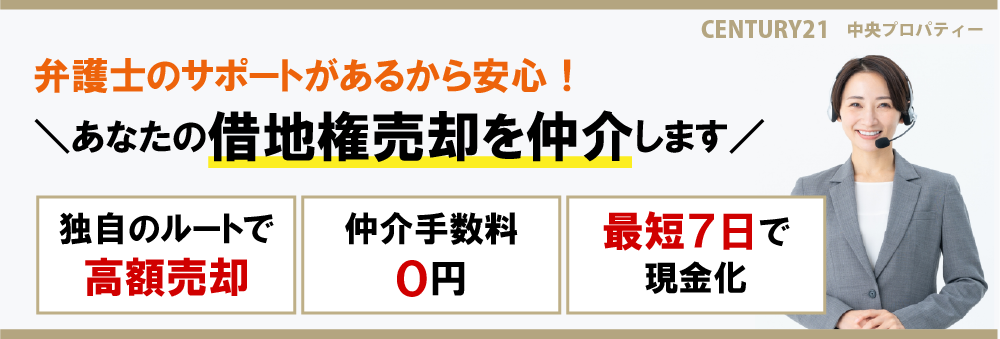
賃借権は相続できる?
賃借権は、相続の対象となります。
賃借権とは、貸主が物を使わせて収益を得る権利を借主に与え、借主が賃料を支払う契約です。契約終了後、借主は物を返却する義務があります。
民法第896条では「相続開始時に被相続人が持っていた財産に基づく権利はすべて相続人に継承される」とされているため、賃借権も原則として相続の対象となります。
民法第八百九十六条
相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
ただし、賃借人が賃貸人(大家や地主)と「終身建物賃貸借契約」や「期間付死亡時終了建物賃貸借契約」を結んでいる場合には、賃借権の相続はできません。終身建物賃貸借契約では賃借人の死亡により、期間付死亡時終了建物賃貸借契約では一定期間の到来もしくは賃借人の死亡により、賃貸契約が終了します。
複数人で賃借権を相続するとどうなる?
複数人で賃借権を相続する場合、一旦、全員が共有(準共有)する形で賃借人の地位を承継するのが一般的です。
複数人で賃借権を相続した場合の注意点は、以下の2点です。
- 賃料の支払いは相続人全員で按分する必要がある
- 契約を継続させるか終了させるか、全員で協議が必要
準共有になっている場合、賃料は法定相続分に応じて按分が必要です。また、準共有状態の場合、賃貸人はいずれの相続人に対しても、相続後に発生した家賃全額を請求できることになっています。
たとえば、家賃12万円の賃貸物件に住んでいた父が死亡し、母・長男・次男が法定相続人の場合に賃貸人は、3人のいずれに対しても12万円を請求できます。
【法定相続割合】
- 母 持分1/2
- 長男持分1/4
- 次男持分1/4
仮に長男が12万円の請求を受けて全額支払いをした場合、母に対して6万円・長男に対して3万円の負担を求めることが可能です。
なお、賃借人が生前に滞納していた家賃については扱いが異なるため、注意しましょう。滞納していた家賃は相続の発生時に「分割可能な金銭債務」とみなされることから、複数の相続人がいる場合は各自で、法定相続分に応じた金額を支払います。
たとえば、上記の例で24万円の滞納家賃があった場合に母・長男・次男は、以下の金額を支払わなくてはなりません。
- 母:24万円×1/2=12万円
- 長男、次男:24万円×1/4=6万円
※準共有状態のとき、家賃の滞納を理由として賃貸人から契約解除を求める際には相続人全員に対し、手続きを行うことが必要です。相続人の1人が対象の建物に居住している場合であっても全員に対して手続きを行わなければ、解除の効力は発生しません。
また、賃借権は相続によって自動的に終了するものではなく、相続人が契約を引き継ぐのが原則です。今後の賃貸借契約をどうするかについては、相続人同士で協議し、引き続き賃借するか、契約を終了させるか決める必要があります。
賃借権を相続したらどうすればいい?
賃借権を相続した際の望ましい対応は、賃借権を使用し続ける場合・解消する場合で異なります。土地の賃借権を相続した場合にはさまざまな費用が発生することから、権利を放棄する方法も選択肢です。以下では、さまざまなシチュエーションを取り上げて、賃借権を相続した場合の対応を具体的に解説します。
賃借権を使用し続ける場合
賃借権を相続して住み続ける場合には遺産分割協議を行い、権利を承継する相続人を決定します。遺産分割協議とは相続財産を分け合うために関係者が話し合い、遺産分割協議書を作成することです。以下は、相続が発生してから遺産分割協議書を作成するまでの流れを示します。
- 相続人と相続財産を把握し、確定させる
- 財産目録(相続財産の一覧表)を作成する
- 相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を経て決定した賃借権の相続人は、「自分が権利を取得した」と、賃貸人に報告します。賃貸人の報告後は賃借権の相続人が家賃や地代の全額を支払いますので、対象の不動産を使用・収益することが可能です。
なお、相続財産が多くて遺産分割協議がまとまらない場合などには相続人に不利益がない限り、賃借権の扱いのみを先に話し合うことも認められます。その場合は賃借権のみに関する遺産分割書を作成して、「一部分割」である旨を明記しましょう。
賃借権を解約する場合
対象の不動産を誰も使用しない場合に放置すると賃貸借契約が継続し、家賃や地代を請求されてしまいます。家賃や地代の支払いを逃れるためには速やかに、賃貸借契約を解約しましょう。賃借権を解約する場合の注意点は、以下2つです。
- 賃貸借契約の中途解約条項に従った手続きが必要である
- 相続放棄できなくなる可能性がある
賃貸借契約では通常、「賃借人から契約を解約する際には1か月前までに申し出る」などの中途解約条項が定められます。賃借権を相続した場合でも中途解約条項が無効になることはないため、契約内容に従って手続きを進めます。
相続放棄とは、相続財産を継承する一切の権利を放棄することです。賃貸借契約を勝手に解約した事実が「相続財産の処分」とみなされる場合は相続財産の継承を認めたとされ、相続放棄できなくなる可能性があります。「賃貸借契約の解約が相続財産の処分にあたるか」は裁判でも判決が分かれているため、相続放棄を少しでも考えている場合は、対応に注意しましょう。
賃借権を相続放棄する場合
土地の賃借権が借地権の場合、対象不動産の評価額・借地権割合に応じた相続税の支払いが必要です。土地の上に住宅などを建てて住んでいた場合には、地代や建物に対する固定資産税・都市計画税の支払いも発生します。さまざまな支払いを負担に感じる場合には、相続放棄する方法も検討しましょう。
賃借権を相続放棄するためには、相続の発生から3か月以内に家庭裁判所へ、相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票などの必要書類を提出します。提出した書類が受理されれば、相続放棄の手続きは完了です。ただし、相続放棄の効力は賃借権以外の相続財産すべての権利義務にも派生しますので、相続放棄の手続きを行う際には自分自身にとってのメリット・デメリットを包括的に考え、冷静な判断を行いましょう。
賃借権の相続にまつわるトラブル
不動産、とりわけ土地の賃貸借契約(借地権に限らず、土地の一時使用権も含む)における賃借人が死亡した場合、賃貸人とさまざまなトラブルが発生するケースもあります。たとえば以下2つは、土地の賃借権の相続で起こりやすいトラブルです。トラブルの詳細と対処法を事前に把握し、万が一の事態に備えてください。
立ち退き要求
賃借権の相続人が賃貸人に連絡すると「相続を許可しない」「一代限りと約束していた!」などの理由で、立ち退きを要求されるケースがあります。
| 【対処法】 賃借権の相続人は特別な対抗要件を備えていなくても賃貸人に対する権利を主張できることから、「相続を許可しない」などの主張は通りません。 また、仮に「一代限り」の特約があったとしても法律上は無効です。立ち退きを拒否しても執拗な要求を受ける場合は、弁護士に相談しましょう。 |
地代の値上げ
相続の連絡を1つのきっかけとして、賃貸人が地代の値上げを要求するケースもあります。
| 【対処法】 相続人は以前からの契約条件を引き継ぐことが原則であるため、値上げに応じる必要はありません。 しかし、相場と比較して明らかに低い相場で契約している場合には強制的に値上げされる可能性もあるため、相手方の要求の妥当性を検討しましょう。 |
地代の相場の計算方法には路線価から算出する方法、周辺地域の地代を参照する方法など、複数のパターンがあります。自分自身で計算できない場合には不動産鑑定士に相談し、アドバイスをもらうことも大切です。
土地の相続にまつわるトラブルは、以下の記事でも解説しています。よくあるトラブルや対策をより詳しく知りたい場合は合わせて、参考にしてください。
関連記事:借地権の相続時に気を付けるポイントとよくあるトラブルを解説
賃借権の相続に関連する特殊なケース
賃借権はさまざまな状況で相続されることがありますが、その中には特殊なケースも存在します。最後に、特殊なケースのときに賃借権がどう適用されるのかを解説します。
公営住宅の場合
公営住宅の賃借権は一般的に相続されません。したがって相続人であっても、公営住宅の賃借権を直接引き継ぐことはできません。
もし仮に相続人が公営住宅に住んでいても、正式な手続きを経ない限りは退去を求められる可能性があります。
これは公営住宅が、特定の条件を満たす住人に提供される社会的な住居だからです。公営住宅は自治体によって、入居を継続できる条件が異なります。たとえ以前の入居者、つまり被相続人がその入居要件を満たしていた場合でも、相続人が同じ条件を満たしているとは限りません。もし入居要件を満たしていなかったら、賃借権は適用されなくなります。
賃貸物件に同居している内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者は法律上の相続人ではないため、賃借権を直接相続することはできません。
しかし、相続対象となる相続人がほかにいる場合は、賃貸物件に住み続けることが可能です。これは、相続人が自身に付与された賃借権を内縁の配偶者に利用させる、すなわち賃借権を援用することで実現できます。
一方で、相続人となる人がいない場合、内縁の配偶者は賃貸物件に住み続けることができません。相続人の賃借権を援用することができないためです。
賃借権の援用とは、賃借権を有する相続人がその賃借権を利用して、他者に賃貸物件に住む権利を与えることを指します。具体的には、相続人が賃貸人と協議し、内縁の配偶者を含む同居者に引き続き居住する許可を得ることで成り立ちます。
まとめ
賃借権は特別な契約を結んでいない場合は通常の相続財産と同じように被相続人に相続されます。相続した賃借権はそのまま使い続けることもできる一方、使用しないときは契約の解除や相続放棄も可能です。土地の賃借権では特に地主と借主の間でトラブルが発生しやすいため、何か不明点があれば専門家に相談するようにしましょう。
中央プロパティーでは、相続した借地権の売却について、手厚いサポートを行っています。相続や借地の専門家も多数在籍しているため、借地の相続でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
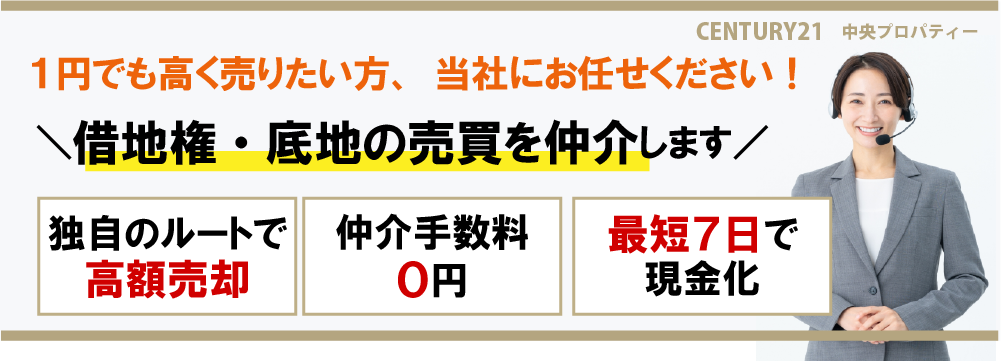
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。





