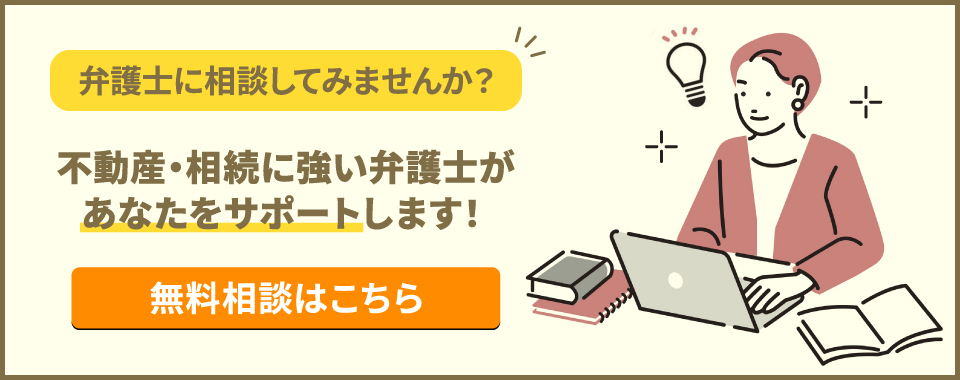借地権の立ち退き料相場は?地主との交渉方法や補償額を上げるポイント
借地権の立ち退き料相場は?地主との交渉方法や補償額を上げるポイント

目次
借地権の立ち退き料は、借地人が土地を必要とする事情や立ち退きの理由などによって左右されます。
一方で、契約の内容や借地の状態によっては立ち退き料を受け取れないケースもあり、注意が必要です。
当記事では、借地権の立ち退きに必要な正当事由や、立ち退き料の金額を決定する要素について詳しく解説します。
地主から立ち退きを要求されている借地人の方は、交渉を有利に進めるために当記事をお役立てください。
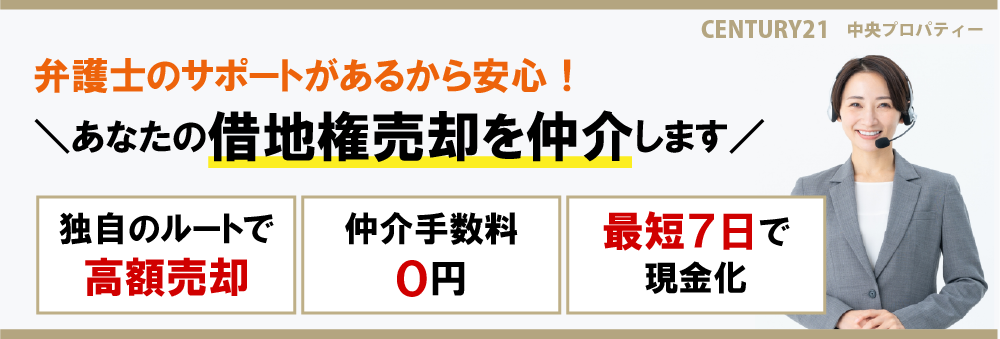
本来、地主が借地人に立ち退きを求めるためには「正当事由」が必要
借地契約においては、賃貸人である地主が借主である借地人に対して立ち退きを要求する場合、正当事由が求められます。
ただし、地主が主張する根拠が正当事由に該当するかどうかは裁判所の判断となり、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。
したがって、「こういった根拠があるから必ず正当事由として認められる」とは言い切れません。
地主が借地人に立ち退きを主張する正当事由としては、以下のものがあります。
- 地主が土地を利用したい
- 借地上の建物が朽廃・老朽化している
- 借地人に契約不履行がある
- 地主が借地人に対して、すでに立ち退き料を提示している
地主が土地を利用したい
地主が土地を利用したいという理由は、立ち退きを求める正当事由の一つとなり得ます。
例えば、今ある建物を取り壊して別の建物を建てたい場合などです。
もう少し具体的に説明すると、以下のような状況が該当します。
- 地主本人やその家族が居住するために、自宅を新たに建築したい場合
- 隣接地にある地主の企業が、営業所や工場を増設するために土地が必要な場合
- 借地人がその土地を自ら利用せず、賃貸物件として第三者に貸している場合
地主・借地人双方にとっての土地の必要性を比較し、地主側の事情がより正当であると判断された場合は、立ち退きの要求が認められる可能性が高くなります。
もし借地人が別の場所に住居や建物を所有している場合、地主側の要求が認められやすくなります。
これは、借地人が立ち退きにあっても生活を脅かされないと裁判所が判断する可能性が高いためです。
また、地主の厚意で貸し始めた場合や、地代が相場よりも格安な場合は特に地主側の主張が認められやすくなります。
借地上の建物が朽廃・老朽化している
建物の状態も、立ち退きの正当事由となる場合があります。
特に、建物が倒壊するおそれがあって危険なときは、地主側の要求が認められることがあります。
老朽化が進んだ建物は、倒壊などにより周辺に危険を及ぼす可能性があるため、公共の安全にも関わる問題となるからです。
ただし、単に建物が古くなったという程度では、立ち退きの正当事由として認められる可能性は低いでしょう。
住んでいる人に危険がおよぶリスクがある場合は、比較的認められる可能性が高くなります。
建物の朽廃・老朽化が正当事由として認められやすい状況の例▼
- 老朽化に伴って建物の構造が劣化している
- 老朽化が進行して耐震性が著しく低くなっている
- 基礎部分が腐食していて、修繕しても改善が見込めない
また、必要な修繕を怠ったなど、建物の状態が悪化した原因が地主側にあるときは、地主側の要求が認められる可能性は低くなります。
借地人側に契約不履行がある
例えば、借地の地代未払いが続いている場合、借地契約の解除が認められ、借地人は立ち退きを拒否することが難しくなります。
同様に、地主に無断での増改築や契約内容に反した利用があった場合も、立ち退き拒否が困難になります。
ただし、軽微な違反や一時的な遅延などの場合は、即座に立ち退きの理由とはならない場合もあります。
もし裁判で争うことになった場合、裁判所は違反の程度、契約不履行の内容、是正の可能性などを総合的に判断します。
地主が借地人に対して、すでに立ち退き料を提示している
ここまで解説しました理由に加えて、地主が借地人に対して相応の立ち退き料を提示している場合、正当事由として認められやすくなります。
しかし、あくまで正当事由として認められる可能性が高くなるだけで、必ず立ち退きを命じられるわけではありません。
立ち退き料の金額の妥当性や、借地人の具体的な状況(生活や事業への影響など)を考慮して判断されます。
立ち退き料には、賃借人の移転費用、営業損失、新たな物件を探す際の仲介手数料などが含まれ、借地人の損失を補填する役割を担います。
また、借地人が長年住み慣れた土地を離れることに対する、精神的な負担への補償なども考慮される場合があります。
借地権の立ち退き料の相場は?
結論、立ち退き料に相場はありません。
立ち退き料の金額は当事者である賃貸人・借主の話し合いによって決められるのが一般的です。
ただし借地権の場合は、借地権価格が目安となる場合があります。
借地権価格は、次の計算式で求めます。
| 借地の評価額 × 借地権割合 |
借地権割合は、国税庁のウェブサイトで調べることが可能です。
出典:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
上記の算出方法で求めた借地権価格をもとに、さまざまな事情を考慮しながら立ち退き料が決まります。
具体的には、借地権の補償・転居および移転先の敷金礼金・賃料差額補償など、借主の経済的損失に対する補償が加味されるケースがほとんどです。
また、立ち退きを要求される借主が個人か事業者かによって補償の内容が変わります。
個人向けの補償には引っ越し費用の補償、事業者向けには移転費用の補償・営業補償などが支払われるのが一般的です。
地主から立ち退きを求められた場合、借地人はどうする?
地主から立ち退きを求められた場合、借地人は冷静に考え、自身の権利を守るための適切な対処が求められます。
ここからは、借地人が確認すべきポイントや、立ち退きまでの一般的な流れを解説します。
借地人が確認すべき3つのポイント
立ち退きを求められたとき、借地人が確認すべきポイントは以下の通りです。
- 借地契約書を確認し、自分の権利や契約条件を把握する
- 立ち退き料の目安を調べ、適正な補償額を把握する
- 借地権に詳しい弁護士や不動産会社に相談し、助言をもらう
①借地契約書を確認し、自分の権利や契約条件を把握する
立ち退きを求められたら、まず借地契約書を確認し、自分の権利や契約条件を正確に把握します。
契約期間や更新履歴、契約終了の条件をチェックしましょう。
また、過去の地代の増額履歴なども確認しておけば、交渉材料にすることができます。
例えば、過去に地代の増額を受け入れてきた場合、借地人がこれまで地主の要請に応じてきた実績として、立ち退き交渉で有利に働くことがあります。
契約書の内容が不明確な場合や、口頭での約束事項があるときは、それらを整理し、できるだけ文書化しておくことが望ましいです。
これらの情報は、後の交渉や裁判で重要な証拠となる可能性があります。
②立ち退き料の目安を調べ、適正な補償額を把握する
判例や過去の事例を参考にしながら、同じようなケースの立ち退き料の相場を調査し、地主から提示される金額が妥当かどうかを判断する材料にしましょう。
具体的には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する、弁護士に相談して類似の裁判例を調べてもらう、不動産会社に相談して近隣の取引事例を教えてもらう、などの方法があります。
③借地権に詳しい弁護士や不動産会社に相談し、助言をもらう
立ち退きに関する情報は複雑で、公的な判断基準が明確に定められていないため、借地人にとって正しい情報を見つけにくいのが実情です。
特に、立ち退き料の相場や適正な補償額の算定方法はケースごとに異なり、一般の方が自身で正しく判断することは非常に困難であると言えます。
したがって、弁護士や不動産の専門家に相談し、契約内容の確認や、借地人が主張できる権利を整理してもらうのがおすすめです。
借地借家法に詳しい弁護士に相談すれば、交渉の進め方や注意点について具体的なアドバイスを受けられます。
また、不動産鑑定士に依頼することで、立ち退き料の適正な相場を把握できます。
弁護士が所属する法律事務所や不動産会社の中には、無料相談を受け付けているケースもあります。
まずはそういったサービスを利用して、自分の状況を整理することも一つの方法です。
立ち退きまでの流れ
立ち退きを要求されたときの一連の流れは以下の通りです。
- 通知書の確認
- 地主との交渉
- 立ち退きの裁判
Step1.通知書の確認
まずは地主から立ち退きを求める通知書が送られてきます。
通知書には立ち退きの理由や対応期限が記載されています。
多くの場合、内容証明郵便で送付されます。
通知書を受け取ったら、まずはその内容をよく確認しましょう。
立ち退きの理由が正当なものかどうか、要求されている立ち退き期日は妥当かどうか、立ち退き料の提示があるか、ある場合はその金額などを確認することが重要です。
Step2.地主との交渉
続いて、地主と借地人で交渉を行います。
交渉の場では地主の主張を改めて確認し、立ち退きを求める具体的な理由や条件を把握します。
また、立ち退き料や期限など、交渉の場で提示された条件も確認しましょう。
地主の言い分を聞くのと同時に、借地人側の主張も交渉の場で伝える必要があります。
今の建物を使い続ける必要性や、立ち退く場合の損失などを具体的に説明しましょう。
例えば、長年住み続けている場合は、生活の基盤がその場所にあることを説明するのが有効です。
通勤や子どもの通学に支障が出ること、地域とのつながりが深いことなど、立ち退きによって生じる影響を具体的に伝えましょう。
交渉では、できるだけ感情的にならず、冷静に対応することが大切です。
地主との交渉内容や、地主からの提示を書面で残すようにしましょう。
また、弁護士に同席してもらうことも検討しましょう。
Step3.立ち退きの裁判
双方の協議で解決しなかった場合は、裁判を行うことになります。
裁判に発展すると、判決までに時間を要することが多いです。
裁判所は立ち退きの根拠として正当事由があるか、正当事由の内容は妥当かどうか、立ち退き料の金額は適切かなどを基準に判断します。
これまでの交渉経緯や提示された条件なども重要な判断材料となります。
そのため、交渉の段階から証拠を適切に保管しておくことが重要です。
立ち退きに納得できない場合はどうする?
もし立ち退きの申し出に納得できない場合、第三者を介入させ、冷静に交渉を進めるようにしましょう。
協力してくれる第三者としては、弁護士や、借地権トラブルの解決実績やノウハウがある不動産会社などが挙げられます。
なお、可能であれば、交渉が難航してからではなく、事前に専門家に相談、し必要なサポートや助言を受けるのが望ましいです。
また、交渉がうまくいかない場合は調停や裁判を視野に入れ、必要な証拠を準備することも重要です。
例えば、これまでの地代支払いの記録、建物の維持管理状況(修繕履歴など)、地域との関係性を示す資料などが有効な証拠となる可能性があります。
さらに、調停を申し立て、第三者を介して和解を目指す方法もあります。
調停は裁判よりも柔軟な解決が可能で、時間と費用の面でもメリットがあります。
調停では、両者の主張を聞いた上で、調停委員が公平な立場から解決案を提示します。
借地人が立ち退き料をできるだけ高く受け取るための4つのポイント
もし立ち退きの要求が認められた場合、借地人は慣れ親しんだ土地を離れ家を手放すことになります。
借地人としては土地を明け渡す代わりに、立ち退き料をできるだけ高く受け取りたいと思うでしょう。
借地人が立ち退き料をより高く受け取るためのポイントは以下の通りです。
- 借地の使用を継続する必要性が高いことを主張する
- 更新料の支払いを証明する(過去に更新料を払っている場合)
- 早期立ち退きを条件に立ち退き料を高くしてもらう
- 「建物買取請求権」で建物を地主に買い取ってもらう
借地の使用を継続する必要性が高いことを主張する
立ち退きの正当事由にも挙げられる「土地使用の必要性」については、立ち退き料の設定でも強い意味を持ちます。
借地人にとって土地の必要性が高ければ高いほど、立ち退きによって受ける不利益が大きいため、立ち退き料も多く受け取れる可能性があります。
借地人自身が借地上の建物に住んでおり、それ以外に借地人が所有している宅地や建物がない場合は、借地人側に有利に働きます。
土地使用の必要性がある場合は積極的に主張するのがおすすめです。
更新料の支払いを証明する(過去に更新料を払っている場合)
借地契約書や地域の慣習で更新料の定めがある場合、その支払いを適切に行っているかは立ち退き交渉において重要なポイントです。
もし支払いを怠っていると、契約不履行(債務不履行)として信頼関係が損なわれたと見なされ、契約解除の理由とされたり、交渉で不利な立場に置かれたりするリスクが生じます。
反対に、領収書や振込記録などで支払いをきちんと証明できれば、誠実に契約を守ってきた客観的な証拠となり、地主からの信頼関係に関する主張に対抗しやすくなります。
これにより借地人側の交渉上の立場が強化され、結果として有利な立ち退き条件(立ち退き料を含む)を獲得しやすくなるため、支払いを示す証拠書類は大切に保管しておきましょう。
早期立ち退きを条件に立ち退き料を高くしてもらう
地主が早くその土地を使いたいと考えている場合であれば、早期立ち退きを条件に立ち退き料を高くしてもらうことも可能です。
ただし、立ち退き交渉の経験が豊富な地主の場合は、知識のない個人が交渉を行っても思うように進まないケースも少なくありません。
地主への交渉がうまくいかない場合は、不動産トラブルに精通した弁護士など、専門家に相談することで、交渉のコストや労力を抑えられます。
「建物買取請求権」で建物を地主に買い取ってもらう
借地であっても、借地人が建てた建物の所有権は借地人にあります。
借地人が立ち退きを要求された際、借地に建てた建物を時価で買い取るよう、地主に請求することが可能です。
地主に建物の買取を求める権利を「建物買取請求権」と言います。
借地人が建物買取請求権を行使した場合、地主は請求を拒否できません。
ただし、建物買取請求権を行使するには、以下の要件を満たす必要があります。(借地借家法第13条)
- 借地上に建物が存在すること
- 借地権の存続期間が満了し、更新がないこと
立ち退きの際には、借地人は建物を取り壊して更地にするよう求められるのが一般的です。
一方、建物の買取が成立すれば、借地人側で建物の取り壊しを行う必要がなくなるため、取り壊し費用がかかりません。
借地人が立ち退き料を受け取れないケース
一般的に、地主から借地人に対して立ち退きを要求する際には、立ち退き料の支払いが必要です。
しかし、借地人が地主に立ち退き料を請求できないケースも存在します。
契約内容や、契約中の借地人の行動によっては、立ち退き料の請求が認められない場合があるため注意が必要です。
借地人が立ち退き料を受け取れない可能性があるケースは、以下の通りです。
- 借地人に契約違反がある場合
- 定期借地契約・一時使用目的の借地権・建物譲渡特約付借地契約の場合
- 建物を建てることを目的としない借地契約の場合
借地人に契約違反がある場合
地代の滞納など、借地人側が契約違反を行っている場合は、債務不履行を理由に借地契約は解除されますので、立ち退き料の請求はできません。
そして、契約違反による立ち退きの場合、借地人は契約解除後ただちに建物を取り壊し土地を明け渡すことが義務付けられています。
無断転貸も契約違反です。
借地権の転貸とは、例えば、借地人が地主から土地を借りたが、建物を建てずに第三者(転借人)に土地を貸し、第三者が建物を建てたような場合を指します。
地主の許可なしに借地権を転貸すると、地主は契約解除を求めることが可能であると定められています。
建物の増改築・取り壊しを、無断で行うのも契約違反です。
地主の許可なく建物を増築・改築したり、取り壊したりする行為は禁じられています。
借地契約は「借地上に建物があること」が前提です。
したがって、無断で取り壊すと契約違反になります。
また、契約で定めた用途とは異なる目的で土地を利用する行為も、契約違反に該当します。
例えば住居専用の借地に無断で店舗や事務所を開いたり、駐車場を開設したりすると契約違反となります。
借地人によるこうした行為が発覚した場合、契約違反があったとされ、立ち退き料が受け取れなくなる可能性が高まります。
定期借地契約・一時使用目的の借地権・建物譲渡特約付借地契約の場合
契約更新が認められない借地権では、契約満了の場合立ち退き料は発生しません。
一定の条件で契約が満了するのは、以下の契約の場合です。
| 定期借地契約 |
|---|
| 期間の定めがある借地契約です。基本的に契約の更新はできません。 |
| 一時使用目的の借地 |
|---|
| 住居建て替えの際の仮住まいや、店舗改装時の仮店舗など、一時使用を目的とする契約です。契約書に一時使用である旨が記載されている上、客観的にも一時使用目的であると認められる場合にのみ締結できます。 |
| 建物譲渡特約付借地契約 |
|---|
| 借地権設定から30年以上が経過した場合、地主が建物を買い取ることを定めた契約です。建物を地主に売り渡した際に契約が終了します。 |
建物を建てることを目的としない借地契約の場合
駐車場として使われている土地、太陽光発電のための土地など、建物を建てることが目的でない場合は、借地借家法で定められた「借地」にそもそも当てはまりません。
借地権は借地上に建物が建っていることが条件となるため、それ以外のケースでは立ち退き料は支払われません。
立ち退き料にかかる税金
立ち退き料は課税対象であり、税金を払う必要があります。
地主が立ち退き料を支払った場合は、経費として計上可能です。
経費の種類は立ち退きの目的によって異なります。
| 立ち退きの目的 | 所得区分 |
|---|---|
| 貸し出した建物・敷地を譲渡する場合 | 譲渡所得として控除 |
| 上記以外の理由 | 不動産所得として必要経費に計上 |
また、借地人が立ち退き料を受け取った場合は確定申告が必要です。
立ち退き料の所得区分は、立ち退き料の性質によって変わります。
| 立退料の性質 | 所得区分 |
|---|---|
| 借地権など権利の対価に相当する金額として支払われる場合 | 譲渡所得 |
| 店舗物件などからの立ち退きに際する立退料 | 事業所得・雑所得 |
| その他の立退料 | 一時所得 |
立ち退き料には消費税が課税されることもあります。
立ち退き料の場合、国内取引かつ事業者による事業で対価を得ている取引の場合のみが課税対象です。
借地権の立ち退きに関するよくあるご質問
借地権の立ち退きに関して、よくある質問は以下の通りです。
- Q.地主から立ち退きを求められた場合、借地人は拒否できますか?
- Q.立ち退き料はどのように計算されますか?
- Q.地主に借地契約の更新を拒否された場合、借地人はどうすれば良いですか?
- Q.立ち退きに応じた場合、借地上の建物の解体はどうなりますか?
- Q.老朽化を理由とした立ち退きは認められますか?
Q.地主から立ち退きを求められた場合、借地人は拒否できますか?
A. 地主(賃貸人)が一方的に立ち退きを要求することは認められていません。
しかし、借地人に契約違反などがあれば、立ち退きに応じなければならない場合もあります。
Q.立ち退き料はどのように計算されますか?
A. 立ち退きを求められた場合、補償金として立ち退き料を求めることができます。
立ち退き料は、借地権者の経済的損失や、土地を離れることによる不便に対して支払われることがあります。
立ち退き料については、交渉や法的手段を通じて決めることができるため、専門家に相談し、自分に適切な補償を求めることが大切です。
Q.地主に借地契約の更新を拒否された場合、借地人はどうすれば良いですか?
A. 借地契約の更新拒否には正当な理由が必要です。
理由が不当だと感じる場合、弁護士を通じて法的に争うことが可能です。
また、契約に記載された更新の条件を確認し、更新に関する交渉を行うのも一つの方法です。
Q.立ち退きに応じた場合、借地上の建物の解体はどうなりますか?
A. どのような内容で、立ち退きに合意したかによって異なります。
立ち退き料を受け取る代わりに、建物の解体費用を借地人が負担するケースもあれば、建物を解体しなくてもよいケースもあります。
Q.老朽化を理由とした立ち退きは認められますか?
A.単に建物が古くなっているだけでは、それ自体を理由とした立ち退き要求が認められる可能性は低いです。
老朽化が著しく進行していて、建物の構造が劣化していたり、耐震性に問題がある状態になっていたりするなど、居住者や近隣に危険が及ぶ可能性がある場合は、地主からの立ち退き要求(契約の更新拒絶)の正当な理由の一つとして認められやすくなります。
地主が、建物の老朽化といった事情を含めて借地契約の更新を望まず、契約を終了させたい場合、借地権者が契約の更新を請求したときや、期間満了後も土地の使用を継続しているときは、地主は遅滞なく異議を述べる必要があります。
ただし、この異議だけでは契約終了の効果は生じず、更新を拒絶するためには、地主側の土地使用の必要性、借地人の土地使用の必要性、建物の老朽化の程度、これまでの経緯、立ち退き料の提供の申し出など、諸般の事情を考慮した上で判断される「正当事由」が存在することが法律上必要となります(借地借家法第5条、借地借家法第6条)。
立ち退きを求められときはすぐに相談しよう
地主から立ち退きを要求された場合、借地人には立ち退き料を請求する権利があります。
立ち退き料の金額は、借地人側がその土地を引き続き使用する必要性の高さや、地主が求める早期の立ち退きに応じるかどうかといった様々な要因で変動します。適切な補償を得るためには、地主との交渉が非常に重要になります。
もし地主との交渉に不安がある場合や、ご自身での対応が難しいと感じる場合は、借地権の問題に詳しい弁護士や不動産会社などの専門家へ相談することをおすすめします。
また、立ち退きを求められている状況であっても、借地権を第三者へ売却できるケースもあります。
借地権の売却をご検討中でしたら、ぜひ一度センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。
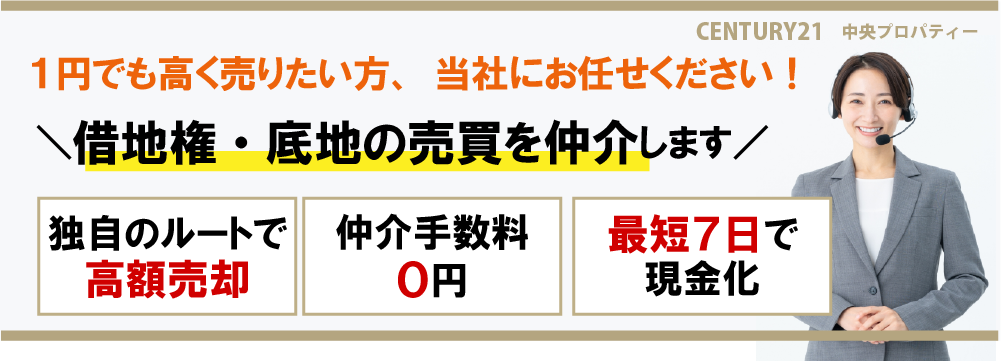
この記事の監修者
社内弁護士
当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。